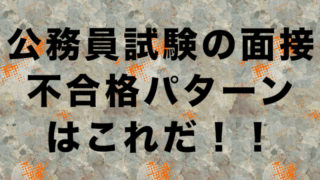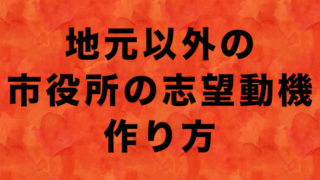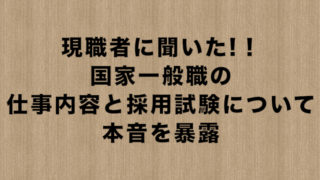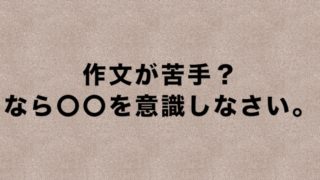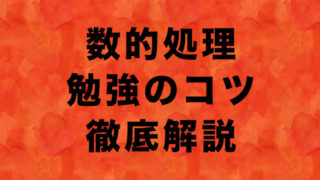論文ってどう書いたらいいの?
ちゃんと書いても文字数が全然足りない・・・
やっぱり論文はセンスか!
悩んでいるあなた。
論文試験ってどう対策したらいいかわからないですよね。
ネット上でもいろいろな意見があるし、いろいろな対策方法があるから何が正しいのか全然分からない・・・
と悩んでいるかもしれません。
私も受験生時代、論文試験の勉強で
これってどう勉強すればいいの?
講座も具体的に教えてくれないし・・・
という悩みを抱えていました。
論文ってどう対策すればいいのか分からないんですよね。
なぜ教えられないのか?
なぜ予備校の対策を受けても論文が上手くなったと思えないのか?
予備校や参考書は「文章を書くことに慣れている人」のためのものだからです。
「文章が苦手」な人は、その前のステップでつまずいているから実践しても腑に落ちないのです。
この記事では、「本当に文章が苦手だと感じているあなた」に読んでもらいたい。
この記事を読むことで、
「そもそも何を書けばいいの?」
「普通に書いたら200字位で終わるんだけど・・」
「まったく書くことが浮かばないんだけど・・・」という悩みを解決することができるでしょう。
それでは、まいりましょう。
Contents
論文は自分の考えを相手に伝えることだ!!
![]() あなたは「論文」と「作文」の違いが分かりますか?
あなたは「論文」と「作文」の違いが分かりますか?
この違いが分かっていないから論文の本質がつかめず、枝葉末節の部分を対策しようとするため、効果的な論文が書けないのです。
いいですか?
「作文は自分が思ったことを書くことであること」に対し、「論文は自分の考えていることを他人に分かってもらう」というものです。
つまり、「論文は、自分の意見を他人に納得してもらう」ための文章なのです。
論文を書けない「3つのnot」を克服しろ
論文が苦手な受験生が多いのはなぜでしょうか?
それはこの「3つのnot」が分かっていないからです。そのため論文に苦手意識を感じるのでしょう。
ちなみに、多くの予備校の講座で論文が書けないのは、この「3つのnot」を意識していないからです。
自分がどのステップでつまずいているか分かっていないから「論文が書けない」という受験生が多く発生しているのです。
予備校の先生はある程度、お勉強ができる人が教えているので、その3つのnotを無意識に超えているのですが、文章を書くことが苦手な人は、この落とし穴にハマっているから論文が書けないのです。
この3つのnotのどれかの落とし穴にハマっているから論文が苦手なのですが、自分がどこの穴にハマっているのかが分かれば、問題は解決したも同然でしょう。
対策の仕方が分かりますからね。
では、論文を書くために踏み越えるべき「3つのnot」とは何でしょうか?
論文が苦手な人が陥っている「3つのnot」
①書くべきことを知らない
②論文を書く材料を作るためにどう考えたらいいか分からない
③どう書いたらいいか分からない
この「3つのnot」について、それぞれお話していきましょう。
3つのnot:①書くべきことを知らない
そもそも論文は何のために書くのでしょうか?
それは、「自分の考えたことを、筋道を立てて説明し、他人に納得してもらう」ためのものでしたね。
つまり、論文は「相手に納得してもらう」ための文章でなければいけないということです。
ですから「私は〇〇だと思う。」などの意見や価値観を伝えるだけではいけないのです。
「AだからBであり、BだからCである。」というように筋道を立てて説明しなければなりませんし、「〇〇が好き」ではなく、「〇〇だから〇〇が好き」と理由を述べていくことが重要ということです。
では筋道立てて説明するには、どうすればいいのか。
文章の構成を意識しましょう。
論文は「何を伝えるか?」「どの順番で伝えるか?」を明確に決めておけばいいのです。
その構成ごとに必要なパーツを集め、それをはめ込んでいくことで、論理的な文章を書けますからね。
具体的には、次の3ステップを意識しましょう。
論文を書くために必要な3構成
①問題提起:与えられたテーマはなぜ問題なのか?
②原因分析:なぜその問題が起こっているのか?
③解決策:その問題を解決するために、行政は何をするべきか?
この型に沿って書くことで、論理的な文章になります。
論文で意識するべきは「パズル」です。
「全体を意識し、各要素に必要な「ピース」を作り、それをはめていく。」というようなイメージですね。
論文を書くための構成についてさらに知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
各要素をどのように書いていけばいいのか?
どのように文章を書いていけば論理的な文章になるのか?
についてわかりやすく説明しています。
https://katigumikoumuin.com/comment/bonbon-itukarataisaku/
3つのnot:②各構成の材料を作るためにどう考えたらいいか分からない
さきほどまでは「論文は構成を意識しろ」というお話でした。この構成にしたがって書けば、合格論文を書くことができるでしょう。
しかし、各構成はどのように書いていけばいいの?という疑問がありますよね。
そのためには「自分の考えを深める能力」が必要です。
論文は相手が納得するように書かなければいけません。そのためには筋道立てて説明する必要があります。
そのためには「なぜそのような主張になったのか?」「なぜそう言えるのか?」について考えておく必要があるのです。
なぜその問題が起こっているのか?
なぜその問題が重要なのか?
その問題はどのような原因で起こっているのか?
行政はその問題をどのように解決していばいいのか?
などについて考えていなければ、説得力のある文章を書くことができませんからね。
でも、「考えることを苦手・・・」と感じている人も多いはず。でも、「どうやって考えれば深めればいいの?」と疑問に思ったかもしれませんね。
考えるには「問い」を持て
論文を書くためには思考を深めなければなりません。「考える」ことをせずに論文を書こうとしても表面をなぞったような論文しか書くことはできないでしょう。
だから、ちまたの論文対策は「暗記することだ」などという本質からずれたことしか教えられないのでしょう。
そもそも自分なりに考えることができれば、知識がないテーマでも合格できる論文は書けるのです。
では、考えを深めるためにどうすればいいのでしょうか。
そのポイントは「問い」です。物事を考えるためには「問い」を意識するようにしましょう。
例えばある部族が深刻な水不足に陥ったとしましょう。
水不足を解消するためには近くの川から水を持ってこなければいけません。
その状況の中、部族の中の誰かが「近くの川からどうやって水を持ってくればいいのか?」という問いを持ったことで、バケツというものが生み出されたのでしょう。
バケツが生み出されたことで「水不足」が解消されたように見えました。
ですがこのバケツで水を運ぶためには、時間がどうしてもかかってしまいます。肉体的にも非常に厳しいことでしょう。
そんな中ある人がこのような「問い」を持ったらどうなるでしょうか?
「水を運ぶのはめんどくさいな。そもそも自分たちが水を運ぶのではなく、水を近くまで持って来るにはどうしたらいいだろう??」
この問いを持ったことで、自分たちで川を作ろうという発想が出てきたのです。
人間は問いを持つことで考えを深めることができるのです。
「なぜりんごが落ちるのか?」という問いを持ったことでニュートンは「万有引力」を発見したように、問を持つことで人間は自分の思考を深める事ができるのです。
この「問いを持つこと」は論文でも意識するべきでしょう。
例えば論文で「少子化の何が問題なのか?」という質問に対し考えを深めるためには、次のような問いを持つことが必要です。
「少子化の何が問題なのか?」
「そもそもの原因は何なのか?」
「なぜそう言えるのか?」
「少子化を解決するために行政が出来ることは何か?」
このように問いを言語化することで、新たな発想や思考が出来るようになるのです。
逆に、考えるのが苦手な人は「言葉」を意識せずに、なんとなく悩んでいるから、浅い考えしかできないのです。
「ダイエットができないな〜」という漠然と考えるのではなく、
「どうすればダイエットができるのか?」
「どうすれば楽に運動が続くのか?」
「どうすれば食欲を抑えられるか?」
「そもそも食欲を忘れるにはどうすればいいのか?」
という問いを持つことで、ダイエットについて考えることができるようになりますよね。
問いを意識することで、考えは深まるのです。
問いを持つことについて、アインシュタインもこう述べています。
もし自分が殺されそうになって、助かる方法を考えるのに1時間だけ与えられたとしたら、最初の55分間は適切な問いを探すのに費やすだろう。
世紀の大天才、アインシュタインもこの「問い」の重要性について指摘しています。
思考を深めるために、論文でどのような問いを作ればいいのか?については、つぎの記事で詳細に説明しているのでご確認ください。
https://katigumikoumuin.com/comment/ronbun-kousei-goukaku/
それぞれの構成で必要な問を持つために必要な知識を説明しています。
主なテクニックとして次のようなものを紹介しています。
- 課題を言い換えろ!!
- 問題文を否定して考えろ!!
- だから何?と問いかけろ!!
- 視座を変えろ!!
このテクニックを知っておくことで
「どのように考えれば論文が書けるのか?」
「どうすれば論理的な思考ができるようになるのか?」
が理解できるでしょう。
3つのnot:③どう書いたらいいか分からない
さきほどは考えを深める方法について説明してきましたが、ここでは考えを深めた結果、どのように文章化していくかについて説明していきましょう。
文章を書く際に意識するべきは「面書き」です。面書きとは下記の本の重要概念なのですが、ここではざっくり説明していきます。
「面書き」を大づかみに説明するとと「重要なキーワードを並べ、それを文章でつなげていく」ということです。
まずどのようなキーワードを使うのか?を決めた後、そのキーワードをつなげるように文章を書いていくということです。
この方法を意識しておくと早く文章が書けるようになるでしょう。
「初めの数行を書いて行き詰まり、途中からどう書けばいいか分からない」という多くの受験生が抱えている悩みが解決するはずです。
ポイントは必要な文章を書き出し、それを後からつなぐイメージです。
「どのような結論を伝えるのか?」を決めて、その結論を伝えるために「なぜそう言えるのか?」「だから何なのか?」「具体例は?」などの「伝えるべきこと・知っていること」をすべて箇条書きで羅列していきましょう。
そして結論を伝えるために「どのようなピースが必要なのか?」「どのような順番で書けば結論が分かりやすいか」などを考えながら「どのようにその文章を並び替えるのか?」を考えていきましょう。
論文を書く際の具体的なステップ
①各構成に従って伝えるべき結論を決める
②結論を伝えるために必要な「理由」「具体例」などをすべて箇条書きで書き出す。
③箇条書きのものを並び替え、それをつなげて文章にする。
というステップで考えれば、文章を書くことが簡単と思えるはずです。
ポイントはゼロから考えるのではなく、
伝えるべき結論を決め、それを伝えるために必要な情報をすべて書き出し、それらを並び替えて文章にする。
ということです。
「文章を書くとはつなげることだ」ということを意識しましょう。ゼロからすべて書ける人なんていないのです。
まとめ:論文は慣れだ
論文で重要なのはこの考え方に慣れることです。
次の3ステップで合格できる論文を書くことができるので、回数を何度もこなし慣れることを意識しましょう。
①論文は構成を意識するべし。
②各構成にあうパーツを作るために考えを深める方法を学ぶこと
③文章は肉付けした文章を並び替えるものだ。
論文は適切なやり方を学び、そのとおりに実践することで得点できる文章が書けるようになるのです。
追伸:予備校の授業や参考書でいくら勉強しても論文に自信がないあなたへ。
どうも山辺です。
「え??お前誰??」
と思われたと思うので、少し自己紹介をしておきます。
私は元Fラン大学出身だったため将来の不安に感じていたため、大学3回生の時に公務員を目指すことを決意しました。
無能だったにも関わらず公務員試験に合格するために様々な知恵を学んだ結果
国家一般職、県庁、市役所(2箇所)、大学法人に内定をもらい、Fラン大学のくせに、みんなが羨む公務員の仕事を選ぶ立場になりました。
私は予備校の授業では論文が全く書けませんでしたが、たくさんの書籍から学んだ思考力、文章力を磨くことで、どんなテーマでも合格レベルの論文が書けるようになりました。
こちらの企画では、
どんなテーマでも合格レベルの論文が書けるようになるための講義を無料で提供しています。
こちらを読むことで、公務員試験の本質が理解できるため、
飛躍的に合格率を高める事
ができるでしょう。
![]()
予備校では聞けない過激な内容をライン講義でお届けしています。