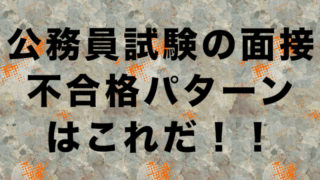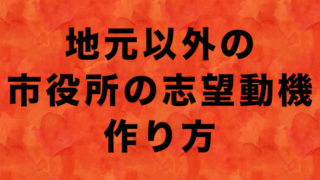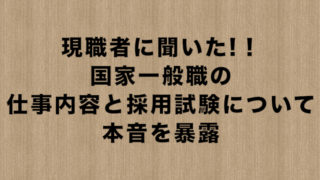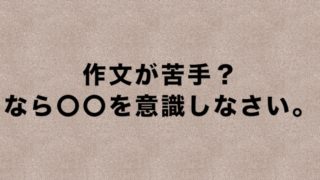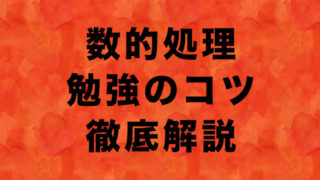「経済学ってどうやって勉強すればいいんだぁあああー」と悩んでいるあなたへ。
経済学ってどうやって勉強すればいいかわからないですよね。
もしあなたが経済学を少しでも勉強しているなら、このように思っているはず。
- 数学が苦手だから経済学は難しい・・・・
- 解説を見ても何を書いているのか分からない・・・
- 勉強していても全く理解できない・・・
そもそも公務員試験で勉強したことって実際の仕事に役に立たないですよね??
なんでそんなに勉強させるのでしょう?笑
ぶっちゃけ公務員試験の勉強をして、仕事に生かせるのは、行政法や民法くらいです。
そのほかの科目なんてまったく意味がありません。
私もイライラしながら勉強していました。
・・・そうはいっても試験で出題されている以上、仕方ありません。
経済学を勉強しないと合格できませんからね。
実は経済学。
ある工夫をすることで、かなり得点源にすることができるのです。
勉強していても「全然分からない・・・」と悩んでいた経済学が、この方法で勉強することでぐんぐんと理解できるようになり、ほぼ正答できるようになりました。(模試などではほぼ9割取れていました。)
「そんなに点数が取れるってもともと頭がいいからじゃないの?」
と思うかも知れませんが、私は大学受験の勉強をほとんどせず、地元のバカ大学に行った人間です。
頭の出来がよろしくありません。
そんな私でも経済学を得点源にし、公務員試験を突破できました。
この記事では、
- 経済学ってそもそもどんな科目なの?
- 経済学ってどのようにべんきょうすればいいのか?
- 経済学を得点源にするためのコツとは?
について説明していきますね。
ちなみに今なら筆記試験に役立つ6つのレポートを完全無料でプレゼントしています。
※こちらのプレゼントは期間限定となっています。
もし必要なら下記リンクよりLINEのご登録をしておいてください。
↓
※個人情報は厳正に取り扱っておりますのでご安心ください。
Contents
経済学(ミクロ・マクロ)ってどんな科目なの?
経済学ってそもそもどのような科目なのでしょうか?
ざっくりいうと、「お金をみんなが使うことを促進する学問」です。
この感覚を掴むことで、経済学が深く理解できるようになります。
「え?どういうこと?」と思ったかも知れませんね。
少しお話しましょう。
むかしむかし、ある村にA君とB君という男がいました。
A君とB君は蓄えがあり、それぞれ100万円を持っていました。
そんなA君は100万円はありますが、家を持っていません。
A君は家がないので、雨に打たれながら生活していました。
そんな生活にA君はうんざり。
「家が欲しい!」と悩んでいましたが、
同じ村のB君が「100万円で家を建て上げるよ」と言ってくれたので、
手元にある100万円で家を建ててもらいました。
その2ヶ月後。
Bくんから家が完成した!!と報告がありました。
その完成した家をみてみると・・・
「すごいいい家だ。」
とA君は大満足。
素晴らしい家の対価としてB君に100万円を支払いました。
その後、A君が家で生活しているのを見て、B君も家が欲しくなりました。
実はB君も家がなかったのです。
そこでA君は、B君に100万円で家を建ててあげることにしました。
B君は大喜び。
B君の手元にある200万円のうち100万円を支払い、家を建てもらうように依頼しました。
その2ヶ月後。
B君の家も完成しました。
A君はB君に素晴らしい家を建ててもらったという感謝の気持ちがあったので、素晴らしい家を建ててあげました。
B君はその家を見て大満足。
その結果、B君も家を手に入れたのです。
さて。
ではこの時、AくんとBくんの手元に何を残っているか確認してみましょう。
Aくんの手元には100万円と家があります。
Bくんの手元にも100万と家があります。
つまり初めはそれぞれ100万円だけでしたが、そのお金をお互いに使い合うことで、それぞれに家が手に入ったのです。
その家でふたりとも幸せに暮らしましたとさ。
めでたしめでたし。
さきほどのお話をしたのは、お金を使うことが社会全体にどのような影響を与えるのか?ということを実感してもらうためです。
A君とB君はお互いに100万円を使うことで、お互いに家を持つ事ができました。
つまり、「みんながお金を使うことで幸せになれる」ということです。
経済は、みんながお金を使えば使うほど、お金が循環し、結果的にみんなが幸せになれるのです。
経済学は、みんなが幸せになるために、
- 国がどのような政策をするべきなのか?
- どのような政策をすれば景気が良くなるのか?
- 逆にどうすれば景気が悪くなるのか?
を解明する学問なのです。
このことを念頭においた上で経済を勉強するようにしましょう。
このよう具体的に考える癖をつけておくことで、理解しやすくなるはずです。
公務員試験における経済学の配点は?
つづいて公務員試験における、経済学の配点についてお話していきます。
各試験での出題数は下記のとおりになっています。
- 国家一般 10/40」
- 特別区 10/40
- 地方上級 11/40
- 市役所 11/40
公務員試験において、経済学はかなり出題が多いですよね。
専門試験の約2割を占めています。
経済学を攻略しなければ、公務員試験の合格はできません。
受験生で「経済学が苦手だから捨てよっかな〜」と考えている人がいますが、絶対にやめておきましょう。
これだけ出題されている科目を捨てるというのは、ほぼ不合格になります。
苦手でも絶対に対策しなければいけないのです。
「経済学が全然わからない」という人も、この記事で書いてある勉強を参考にすることで、出来るようになります。
公務員試験の経済学の難易度は?
公務員試験の中で、経済学は民法と並んで難しい科目とされています。
特に文系出身者に、経済学が苦手な人が多いですね。
多くの人が苦手としている理由は、
経済学には、微分などの数学の素養が必要だからです。
「微分って何?」
「数字を見ただけで鳥肌が立ちそう・・」
このような人にとって、経済学は苦労する科目でしょう。
文系出身者は数学に苦手意識を持っている人が多いですからね。
しかも、最近の公務員試験の難化傾向があります。
そんな経済学を得点するためには、応用力が必要です。
「A」という問題の解法パターンを暗記するだけではなく、問題の原理を理解し、それを応用できなければ、高得点が臨めなくなっています。
そのため多くの受験生が苦手としているのです。
しかし、ここで逆転の発想で考えてみましょう。
多くの人が苦手にしている経済学を得点できれば、有利に公務員試験を戦えるということです。
しっかり対策して得点源にできれば、合格する確率が上がるということです。
ここで頑張れるかどうかが合否の分かれ目なのです。
ではどのように勉強すれば、効率的に理解を深められるのか?について説明していきます。
経済学を効率よく勉強するなら、過去問で勉強しろ!!
公務員試験は「過去問に始まり過去問に終わる」と言われていますが、これは経済学の勉強にも当てはまります。
過去問を勉強することで、問題を解くために必要な前提知識や感覚を効率よく掴むことができますからね。
つまり公務員試験に合格するには、
「過去問をひたすら解け!!」ということです。
シンプルです。
このシンプルな勉強法こそ、最も効率がいい勉強法なのです。
おすすめ過去問は「スーパー過去問ゼミ」だ!!
おすすめ問題集は「スーパー過去問ゼミ」です。
公務員試験ではおなじみですね。
レジュメ、過去問、解説という構成になっており、問題集を解くためにレジュメを確認することで、過去問を解けるようになっています。
特におすすめする理由は、
- レジュメのまとめ方が素晴らしい
- 解説が非常にわかりやすい。
という2点です。
特に解説のわかりやすさはヤバイ。
私は学内講座のテキストで勉強していたのですが、合わなかったので「スーパー過去問ゼミ」で勉強しました。
すると、何度勉強しても理解できなかった問題が一発で理解できるようになったのです。
それぐらいスー過去の解説は分かりやすい。
この問題集を完璧にすれば、9割は得点できるようになります。
私もこの問題集しか勉強していませんが、各試験(国家一般職や地方上級や市役所)で安定してほぼ満点取れるようになりました。
おすすめの参考書は「速習シリーズ」だ!!
過去問を解くことは重要である。
これは間違いない事実ですが、この過去問だけでは応用力が身につきません。
深い理解につながらないですからね。
ですから参考書で、過去問で学んだ知識を整理するようにしましょう。
おすすめ参考書は速習ミクロシリーズの参考書です。
この参考書は豊富な図やグラフを使って、徹底的に分かりやすく説明しており、難しい概念は様々な角度で説明をしてくれているので、経済学を理解するうえで、この参考書は外すことができないでしょう。
さらにこの本の特典として、YouTubeにアップされているこの参考書の解説動画が無料ですべて見ることができます。
この動画をスポット的に扱うことで、効率的に学習できるようになります。
「スーパー過去問ゼミ」と「速習シリーズ」を使ってこのステップで勉強しろ。
さきほどまではオススメ過去問と参考書についてお話してきましたが、これらの教材を使ってどのように勉強するべきか?についてお話していきます。
最も効率よく勉強するには、やはり過去問を初めに押さえるべき。その過去問を解くために参考書で、理解するようにしましょう。
下記のステップで勉強するのが、最も効率が良いでしょう。
具体的な勉強のステップ
- 参考書を片手に、スーパー過去問の基本問題の解説を理解する。
- ①を何度も復習。
- ②が8割ほど理解できるようになったら、応用問題の解説を理解する。
- 勉強した知識が完璧になるまで何度も復習。
このように勉強すれば、合格できるはず。
経済学で高得点を取りたいなら頭の使い方が重要だ。
ここまでおすすめの参考書や問題集とそれらを使った具体的な勉強法について話してきましたが、実はもっと重要な事があるのです。
多くの人がそもそも勉強の効率を上げるためには、どのような問題集や参考書で勉強すればいいのか?ということを考えますが、それだけでは勉強出来るようになりません。
大事なのは頭の使い方です。
その問題集や参考書をどのように理解するのか?という頭の使い方を変えない限り、効率的に勉強することができません。
「弘法筆を選ばず」という言葉があるとおり、勉強できる能力があれば、どの参考書を使っても合格できます。
言葉が悪いですが、バカはバカな頭の使い方を変えなければ、一生バカのママなのです。
もしあなたが効率的に勉強したいなら、頭の使い方を変えなければいけません。
では頭の使い方を変えるにはどうすればいいのか?
「情報を見た時に、どう考えるか?」を意識しなければいけません。
文章の読み方を工夫しなければ意味がない。
私の友達に東大に行った人がいるのですが、そいつは教科書を勉強するだけで東大に合格していました。
当時は「こいつ頭が良すぎるだろ・・」と思っていたのですが、今なら分かります。
多くの人とは頭の使い方が違うので、より大きな結果を出せるのです。
ここでは、どのように頭を使えば、効率よく学習できるのか?について説明していきます。
このポイントを押さえると頭が良くなります。
仕事で「出来る人間」と思われるくらい、頭が切れるようになるはず。
効率よく勉強するなら認知心理学の知見をいかせ
認知心理学って知っていますか?
人間が、外の情報をどのように処理しているかを研究している学問です。
この心理学の知見は勉強に活かせます。
(なぜかほとんどの人はこのことについて触れていないけど・・・知らないんですかね笑)
そもそも人って、物事を理解する時、どのように頭が働いているのでしょうか。
なぜ理解力が人によってことなるのか?
実はこれ、科学的に証明されてしまっています。
頭のいい人はどのような事を考えながら勉強しているのか?が分かっているのです
その前に・・・・
まずは人間はどのように情報を処理しているのか、確認していきましょうか。
ざっと説明すると、次のステップで情報が処理されることが分かっています。
人が物事を理解するまでのステップ
- 意味がわかる?
- 頭に入る?
- 整理できる?
この3つのステップを超えるように勉強することで、理解できるのです。
それではそれぞれのステップについて、具体的に説明していきましょう。
物事を理解するための3ステップ:①意味がわかる?
理解するための初めの壁。
それは意味がわかるかどうか?ということです。
意味が分からなければ、理解できません。
で、この意味がわかるかどうか?は、厳密に言うと
「自分の知識に関連しているものしか意味が分からない。」ということなのです。
人は何かの意味を認識するとき、自分の過去の経験をもとに解釈ができるのですが、
その解釈はすでに自分が知っているものに関連するものしか、意味がわからないのです。
ちょっと分かりにくいですね。
例えば、「صباح الخير」という言葉が何を表しているか分かりますか?
・・・もちろんわからないですよね。
正解はアラビア語で「おはよう」です。
もちろんアラビア語を知らなければ、言葉として認識できませんよね。
このように自分の知識にアラビア語がなければ、人は意味を認識できないのです。
人は「持っている記憶や知識」をもとに解釈をするので、自分の記憶や知識に共通点がなければ、意味が認識できないのです。
ですから勉強する際は、すでに自分にある知識と新たに勉強するテーマに共通点を見つけることをしましょう。
(これを心理学では精緻化といいます。)
では新たなテーマの勉強を、効率的に学ぶにはどうすればいいのか?
そのためには「学問モード」でものごとを捉えなければいけません。
「学問モードって何?」
少し補足しておきます。
人間が「意味が分かる」には2種類あります。
このどちらかのモードで、私達は物事を認識しています。
それは、
①一般モード
②学問モード
です。
例えば、「犬」を言葉で説明してみてみましょう。
あの犬です。
あの犬を言葉だけで説明してみましょう。
・・・結構説明が難しいですよね。
足が4本でワンワンとなく動物?
ですが、犬以外にもい足が四本の動物はいますし、ワンワンと鳴かない犬もいますよね?
「犬」を言葉だけで説明するのは、苦労しますよね。
ですが、「犬」はどれか?と言われたら指をさせますよね。
言葉だけで説明するのは難しいけど、犬というものは分かるはず。
犬の定義を意識しなくても、子供の頃から「あれはワンワン」と教えられ、その言葉を使っているで、言葉で説明することはできませんが、犬というのは理解できます。
このように私達が普段話している言葉や抽象的なワードの意味はいざ言葉で説明すると難しい。
定義は言葉で説明できないけど、その意味はなんとなく分かる。
この定義を求められてもうまく言語化できないけど、意味はわかるというのが「日常モードの学習」と言うものです。
では続いて。
平行四辺形について考えていきましょうか。
平行四辺形を言葉で説明してみましょう。
二組の対辺が平行な四角形
対辺の長さが等しい
対角の大きさが等しい・・・
犬は言葉で定義できないけど、平行四辺形は言葉で説明できますよね。
この平行四辺形は教科書などで「平行四辺形は〇〇だ」と勉強しているから、言葉で説明できるのです。
このように学問や学術では、言葉の定義をしっかりと定め、同じ定義を共有することで、研究が発達しているのです。
定義を理解すること。
これは「学問モード」です。
つまり
「日常モード」・・・定義はわからないけど、具体例を通じて意味がわかるようになる。
「学問モード」・・・定義しているもの
そしてここからが重要なのですが、
勉強はこの「日常モード」ではなく「学問モード」で捉える必要があるのです。
定義を理解しなければ、その定義を使って学習することはできないですからね。
ですがこの定義を理解は、一般モードでしか理解できません。
平行四辺形を知らない状態で、平行四辺形を言葉で説明されても、全然わからないと思います。
あの図があるからこそ、平行四辺形のイメージがわきますよね。
このように学問を勉強するには定義をしっかりと理解しなければいけませんが、この定義を理解するには、具体例がないと理解できないのです。
つまり学問を勉強するためには、日常モードから学問モードのに移動させなければいけないのです。
あなたが経済学を勉強しても分からない理由が分かりましたよね。
定義を浅く理解し、日常モードで捉えようとするから経済学が理解できないのです。
日本語を雑に扱っているから、理解できない。
ではこの定義を学問モードで捉えるにはどうするべきか。
定義を言語化することを常に自問自答していきましょう。
この定義は自分の言葉で説明できるか?を意識するよのです。
理解できない場合は、この定義を掴み損なっている場合がほとんどのはず。
例えば「価格弾力性」について勉強している場合「価格弾力性は〇〇っていう意味かな?」と自分で言語化し、それが合っているかどうかを確認するように勉強するのです。
もし分からないキーワードがあれば意味を正確に掴むようにするべき。
丁寧に言葉を使うことで、解説を見ても「この問題が分からない」ということがなくなるはず。
勉強が分からないのは、言葉を雑に使っているからです。
物事を理解するための3ステップ:②一度に頭に入る?
人はすべてを一回で暗記することはできません。
適度なサイズの情報でないと覚えられないのです。
一度に多くの情報を詰め込もうとすると、すべてを忘れてしまいます。
「これをビール瓶の原理」と私は読んでいます。
ビール瓶に考えなく水を注いでも、ビール瓶に効率よく水を入れることはできませんよ。
適切に注ぐには、小さな口から溢れないように少しずつ水を入れなければいけません。
これは記憶にも同じことが言えます。
キャパを超える情報を大量に暗記しようとしても、すべてが記憶から抜けていくのです。
この場合は少しずつ、適切な量を注がなければいけません。
例えば89435365678という数字を覚えるとしましょう。
このまま覚えようとしてもなかなか覚えられないですよね。
ですが、3桁と4桁に区切るとどうなるでしょう。
894−3536-5678
このように一区切りサイズを工夫すると覚えやすくなりますよね。
人は適度な大きさの情報しか処理できないのです。
ですので、初めは適切なサイズを暗記するようにしましょう。
いきなりすべてを勉強するのではなく、簡単なものから確実に抑えていくのです。
そのあと段階的に範囲を広げていく。
このように複数回に分けて勉強するのです。
具体的にどうやってべんきょうすればいいの?
さきほどもおはなししましたが、記憶するには段階的に勉強することを意識しましょう。
初めは基本問題だけを繰り返し解くのです。
何度も復習していると慣れるので、その後、徐々に難易度が高い問題に手を広げるようにしましょう。
イメージは1つずつ瓦をはめるように勉強するのではなく、ペンキのように重ねながら徐々に手を広げるイメージです。
応用問題や概念が難しいなら初めは飛ばすしましょう。
多くの受験生はそのテーマの問題をすべて解こうとするか頭に残らない、効率が悪い勉強をしてしまう。
一気に勉強するのではなく、各テーマの基本を少しずつ押さえていく。
一度に欲張らず、基本だけを押さえていく。
これを念頭に置いて勉強するようにしましょう。
物事を理解するための3ステップ:③整理できる?
物事を理解するには、覚えた知識を整理するようにしましょう。
ほかの知識と関連付けることで、長期的な記憶できるようになります。
例えば、
149162536496481という数字を暗記するという課題が出されたとしましょう。
あなたならどのように暗記しますか?
丸暗記で覚える??
それじゃー大変じゃないですか?
何かルールはないか。という視点があれば次の法則に気づくはず。
この数字は、1、4,、9,、16、25・・81と並んでいると気づけば、1の2乗、2の2乗、3の2乗・・・9の9乗という法則に従っているのが分かりますよね。
このように自分がすでに持っている知識を関連付けて理解することで、丸暗記しなくても知識を導けるようになるのです。
賢い人は丸暗記なんてしません。
自分の既存知識を関連付けて、頭の中に知識のまとまりを作りながら、記憶しなければ意味がありません。
具体的にどうやって勉強していけばいいの?
先程もお話したとおり、理解するということは、自分の既存の知識をどのように結びつけられるのかが重要です。
情報同士に関連をつけながら記憶しないと、丸暗記に近くなり、記憶が定着しにくくなります。
特に経済学を勉強する上では理解が重要。
丸暗記ではなく、知識ごとに関連を持たせながら勉強するようにしましょう。
経済学は全体でどのような勉強をし、そのテーマは全体のどこのことなのか?を整理しておくことで、理解できるようになるのです。
過去問を解くだけではなく、このテーマごとの関連を自分の頭で作っておくこと。
その工夫をすることで記憶の定着が良くなるのです。
教科書や箇条書きでまとめてある薄い参考書による勉強は、一見楽そうに見えますが、この関連付けるという点で言えば、結局は丸暗記に近くなります。
記憶する量が多くても、その情報に関連性があれば、記憶しやすくなります。
ですので、解説書は例などをふんだんに用いているぶ厚い参考書を使うべきでしょう。
覚える量は増えるかも知れませんが、関連付けて覚えることで、圧倒的に記憶しやすくなるからです。
ちょっと長くなったのでまとめておきます。
理解するためには、次の3つの壁を超える必要がある。
①意味が分かる?⇛解決策:言葉を明確に使うこと。
②頭に入る?⇛解決策:少しずつ範囲を広げる。
③整理できる?⇛解決策:情報を関連させる。
まとめ:経済学は理解!理解の3ステップで勉強していきましょう。
この記事では経済学について説明してきました。
認知心理学を元に理解のステップを説明し、
その説明を元にどのように勉強するべきか?を教えてきました。
この記事でお話したことは、公務員試験以外でも必ず役に立ちます。
ぜひ頑張って勉強していきましょう。
追伸:公務員試験の勉強が思うように進んでいないあなたへ
どうも山辺です。
「え??お前誰??」という声が聞こえてきたので、少し自己紹介をしておきます。
私は元Fラン大学出身から公務員を目指すことを決意しました。
勉強しておらずほぼゼロからのスタートだったのですが、公務員試験に合格するために様々な知恵を学んだ結果
国家一般職、県庁、市役所(2箇所)、大学法人に内定をもらいました。
Fラン大学のくせに、みんなが羨む公務員の仕事を選ぶ立場になったのです。
・・・とはいっても。
私ははじめから上手く言ったわけではありませんでした。
たいして勉強の才能がなかったし、秀でた実績もない、めんどくさがりやのダメダメ人間でしたが、他の人とは違う戦略で戦った結果、圧倒的な成果を出すことができました。
え?その方法が知りたいって?
下記のメルマガでお話ししています。
オンライン講義はラインで行っています。
予備校では聞けない筆記試験の攻略法をメルマガをお届けしています。
↓